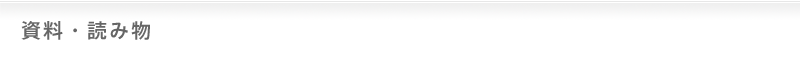2.研究というもの
研究の光と影
研究というのはユニークでないと意味が薄い。テレビの工場なら,年産30万台の工場と10万台の工場は一緒に存在できる。だが,エジソンが電球を発明した翌年に同じものを発明してもほとんど価値はない。研究が成功する裏には,そこに一生を捧げ成功しなかった研究者の累々たる屍が転がっている。
安全な研究は研究か
屍になるのは嫌だからか,近ごろ仲間と同じ研究をする人が多い。成功するとわかっている,実績のあるものにとりついていれば失敗する確率は低い。
だが他人がやったこと,世の中に知られていることをなぞる間は,勉強しているのであって研究とは言い難い。そう定義すると世間の研究のうちで研究と言える部分はわずかで,多くの研究者はその時間のほとんどを勉強に費やして,たとえば国民の血税から月給をもらっていることになる。
それはそれでよい。なぜかというと,次に本当の研究をするときに,勉強の成果がどんと出て,研究を押し進めるのに使われるからである。ただし,一生涯ユニークな研究をしない研究者がいたとすると,それは研究者の待遇に値しない穀つぶしである。
もちろん研究には厚さが必要だから,二番手を走る人やアシスタントに回る人も居てよい。だが,苦心して危険を冒す人と,新しいことはやらず安全運転ばかりの人を同じ研究者として扱ったのでは困る。ところが,日本では前者を異端扱いにする傾向さえある。これでは研究は進歩しない。
原子力船むつ
1974年9月原子力船「むつ」は,原子炉の起動実験でシールドの隙間から放射線が漏れるのが発見され,長いトラブルに突入する。その第一原因はある大新聞が「放射能漏れ」と大きく報道したことにあった。
むつと直接関係はなかったが,放射線計測が専門であった筆者も及ばすながら,「放射線漏れ」と「放射能漏れ」は,光が漏れるか電球が漏れるかほど違うのだなどと各紙の記者に説明したりした。しかし,ホタテ貝の値段が暴落するとか,その恐れがあるなどと混迷を極め,政治が介入し,ようやく1983年に母港は陸奥湾から関根浜への受け入れが決まる。しかし,世界の原子力船は西ドイツのオットーハーン号,米国のサバンナ号ともに,とうに実験を終了して廃船になっていた。
その間の巨大な税金のムダ遣い,従事した研究者/技術者の命運を考えると,こんな対応しかできない社会には,困難を伴うに決まっている新技術の研究に取り組む資格がないとさえ言えよう。
衆愚は誰の責任か
試作した原子炉の最初の起動実験で,放射線が漏れる箇所が見つかったからと,原子力船プロジェクトをぶち壊したのは愚という他はない。当時の放射線シールドの設計では複雑な隙間を通る漏れを,詳しく計算するのは不可能に近かった。どう計算したところで実物との差は必ず存在する。だからこそ実験し,試作し,そのギャップを埋めるのである。
その実験や試作が100%完全にできるなら試作の必要はない。実験や試作では不具合なところがいくつも見つかって当然で,それが進歩の種となる。斬新なことをやろうとすればするほど,生ずる不具合は予測がつきにくいから,実験のトラブルは増える。
そのトラブルで環境や人的に被害が出るようでは困るが,トラブルは新しい発見として歓迎するくらいでなくては,新しい研究などはできない。
風見鶏
報道で気になるのは,各社が同じ切り口,同じ立場になり易い点である。大勢がこうだとなると学者の発言までそれに迎合する傾向がある。あるいは専門家はそれなりの発言をしても,ジャーナリズムがそれを選択して,突出しない安全な意見を採るのでそう見えるのかもしれない。
わが国のジャーナリズムは万人向きの中立公正を装いすぎる。ものの考え方にいつでも中立なコメンテータがいたとすれば,それは無節操な風見鶏にすぎない。底にしっかりした思想,哲学を持った何人か,何通りかの異なった意見があってしかるべきであろう。
幸いにわが国では,たとえ社会の大勢に背く意見でも,国家の方針と異なる見解でも公然と発言できる恵まれた環境にある。それを大いに活用して社会に貢献したいものだ。
-■
(初出:トランジスタ技術,CQ出版社,1996年 7月号 第33巻 第382号 連載2:研究というもの)